人材不足や属人化解消は「地図」にあり ――バス会社が物流向けシステムに見出した可能性
昨今、深刻な人材不足に直面するバス業界。とりわけ、乗務員の高齢化と新規採用の難しさから、効率的な運営と新人教育の重要性が増しています。
大阪府摂津市に本社を置く千里山バス株式会社様(以下千里山バス)も例外ではありません。千里山バスは通勤通学の送迎、冠婚葬祭、観光と3つの領域で中小型バスを提供するバス事業者です。これまでも電子手帳の導入や自社システムの開発など、他社に先駆けて業務効率化に努めてきました。ですが、配車手配や配車計画などの重要な業務は、担当者の長年の知識と経験に依存しており、抜本的な見直しが求められていました。
こうしたなか、千里山バスでは物流向けシステム「ZENRINロジスティクスサービス(以下ロジスティクスサービス)」の導入により、諸問題の解決を図っています。なぜ、バス事業者が物流向けシステムを採用したのか。その背景と成果について、千里山バス株式会社 代表取締役の宮部様と配車担当の市毛様にお話を伺いました。
課題
職人技で属人化した配車計画
ご提案内容
・『配車計画』で車両の最適配車と配送ルートを地図上に可視化
・『固定ルート作成ツール』『ナビゲーション』機能を組み合わせ、ドライバーの自己学習を可能に
導入効果
・配車計画の作成時間が3割削減
・動態管理の導入により緊急時の迅速な対応が実現
・早期人材育成の仕組みを確立
導入企業様

写真左から宮部社長、市毛様
千里山バス株式会社様
【本社】大阪府摂津市東別府3丁目8番32号
【資本金】5,800万円
【従業員数】107名(2024年11月現在)
【事業内容】中型バス、小型バスを専門とした一般貸切旅客運送事業
導入ソリューション
背景・課題
冠婚葬祭・送迎・観光の3つの領域でバス事業を展開
―― まずは御社の事業概要について教えてください。
- 社長
-
当社は、創業51年の中小型専門バス会社です。冠婚葬祭向けのサービスからスタートしており、それまでは主にタクシーが使われていた送迎に、日本で初めて小型バスを採用しました。現在ではこれに加え、通勤通学の送迎や観光も含めた3つの領域で事業を展開しています。
職人技で属人化した配車計画に課題

代表取締役 宮部忍氏
―― 今回、ロジスティクスサービスを導入された背景を教えてください。
- 社長
-
会社の特徴は観光、冠婚葬祭、通勤バスの組み合わせで営業している事です。例えば、朝に通勤送迎へ行ったバスが、日中は冠婚葬祭、夜間はまた通勤、というように、1台のバスを複数の用途で使用しています。バスの台数が約70台。この配車の組み合わせが難しいのです。配車担当者を一人育てるのに5年かかります。配車にあたっては距離的な近さも考慮する為、難易度が高く、配車計画の仕事が職人技で属人的な仕事になっていました。
また、当初から抱えていた課題の一つが「地図」でした。以前から葬儀場やお寺、駅などの配車場所をシステムに登録、カルテで出力できるようにしていましたが、その登録数が3,000か所以上となり、人が覚えるのは難しく地図上への登録の必要性を痛感していました。
属人化は今の時代に合いません。台数も増え人間の力だけでは対応できませんし、地図情報が重要でしたので様々な会社に相談しました。ゼンリンもその一社でした。自動配車と地図の管理をやっていけないかなと思い、声を掛けました。
―― 物流のシステムが御社で活用できると考えられた理由についてお聞かせください。
- 社長
-
物流の場合、決まった場所に荷物を配送しますが、実はバス事業もよく似ています。例えば、葬儀のときには寺院、観光であればターミナル駅といった目的地があります。積むのがヒトかモノかの違いであって、それぞれ所定の位置に配車し、決められたルートを走行する点は物流とバスは似通っています。その為、物流系のノウハウがバスにも応用できるかと思いました。
経緯・導入効果
2年間にわたる検証の末、配車計画の最適化近づく
―― 導入の決め手は何だったのでしょうか?
- 社長
-
導入までの間に、長い時間をかけて配車計画の検証に応じていただいたことが、最終的な決め手になりました。システム導入後もうまく配車できなければ、私たちの事業は成り立ちません。そのためには、より台数が少なく、より最短のルートで問題なく配車できることが求められます。そこで、システムが出してきたルート案と、当社の配車担当者のルートとを比較する検証を2年近くかけ進めました。
とりわけ重視したのは、最小の台数で運用できるようにすることです。例えば、これまで配車担当者が50台で組んでいた配車がシステムで52台必要になるのは避けたい。ですので、そこは徹底して検証しました。
人間が組んだものとシステムが組んだものはまったく違います。ですから、どちらが正解かを判断するのは簡単ではありません。ただ、人の手で組むものは、組み合わせや人員配置に担当者の好みが出てしまい、配車が偏る可能性があります。
2年間にわたる検証の結果、現在はほぼ同じ台数で運用できるようになりました。現在は、配車計画システムで配車しつつも、乗務員のスキルや拘束時間といった要素を基幹システムと照らし合わせながら、担当者の手で調整する運用を採用しています。
配車計画の作成時間が3割削減。動態管理の導入により緊急時の迅速な対応も実現

運行課の市毛俊行氏と動態管理機能
―― ロジスティクスサービスの導入で、どのような効果が得られていますか?
- 市毛様
-
まず、配車については配車計画作成機能を活用することで、作成時間が従来の7〜8割程度に短縮できました。
また、動態管理機能も導入し緊急時の対応が格段に改善されました。日々の業務においてバスがなんらかの理由で運行できなくなることはたびたび発生します。この場合、近くにいて休憩中のバスを配車させるのですが、以前は配車担当者の経験と勘に頼って、代替車両を手配していました。これは担当者の頭の中に「地図」があってからこそできる技で、他の人には真似できません。今回、動態管理の導入により、各車両の現在位置と稼働状況がリアルタイムで把握可能となり、配車担当以外の社員でも最適な代替車両をすぐに選定できるようになりました。
- 社長
-
当社の強みは、お客様の要望に対し「すぐ行きます!」と即答できる、柔軟さです。ロジスティクスサービスの動態管理機能は、この「すぐ行きます」を容易にしてくれました。
固定ルート作成ツールとナビ機能により早期人材育成が可能に
―― 教育面でも活用されていると聞きました。詳しくお聞かせください。
- 社長
-
当社では年間5名から20名ほどの乗務員が入社していますが、40年以上前から50代以上の方を乗務員として迎え入れ、一から教育してきました。一人前の乗務員になるには3,000ヶ所にもおよぶ目的地や60程度のコースを覚える必要があります。従来はこれらすべてを指導員から学ぶ必要があり、相当な時間がかかっていました。
今回、ロジスティクスサービスの固定ルート作成ツールとナビ機能を組み合わせることで、自己学習を可能としました。従来は紙のマニュアルに記載していた停車位置や送迎コースなどの詳細な情報を固定ルート作成ツールに登録し、ナビゲーションを活用することで、経験の浅い乗務員自らが実践練習できる環境を用意しました。指導員と行う実地研修とシステムを使った自己学習を組み合わせることで、人材の早期育成の仕組みが出来てきました。
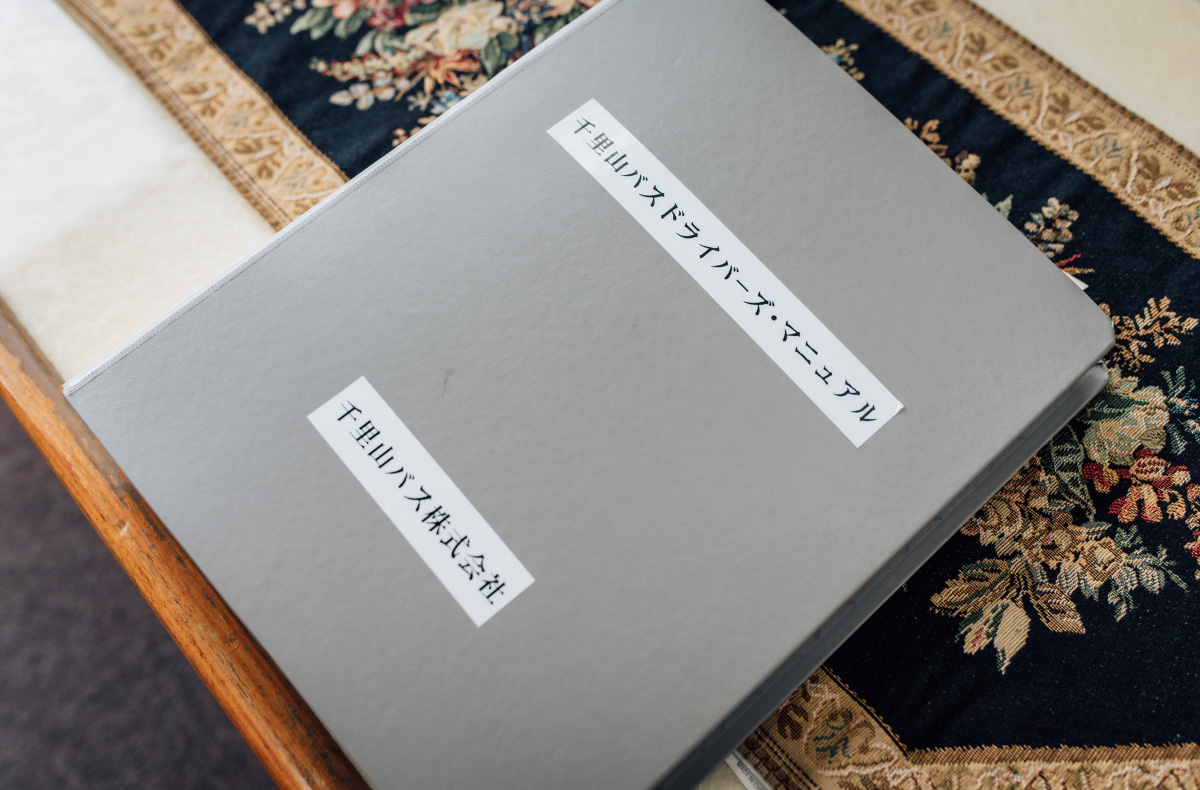
ドライバーズ・マニュアル:送迎コースの詳細情報や停車位置などを記載

乗務員用タブレット端末:固定ルート(送迎コース)を登録しナビゲーションとして活用
今後について
デジタル化は仕事や人生を楽しむための手段である
―― 今後の展望をご教示ください。
- 社長
-
2024年から、ドライバーへの時間外労働の上限規制が適用されます。この規制に対応するには、システマチックな業務管理が不可欠です。人手に頼っていては、これらの条件をすべて満たす配車計画を立てることは困難です。
また、システム化を図ることは、公平かつ明確な評価にもつながると思います。当社では対応できる領域やコースにより乗務員のランク付けを行っています。これを過去の乗務データなどと連携し、評価や処遇に反映させることで、乗務員のモチベーション向上にもつなげていきたいです。
当社の乗務員は、定年までの期間が短い方も多いです。そのため、乗務員には早く仕事を覚え、収入をアップすることで仕事や人生を楽しんで欲しいと考えます、システム導入やデジタル化は仕事や人生を楽しむための手段であると思うのです。




