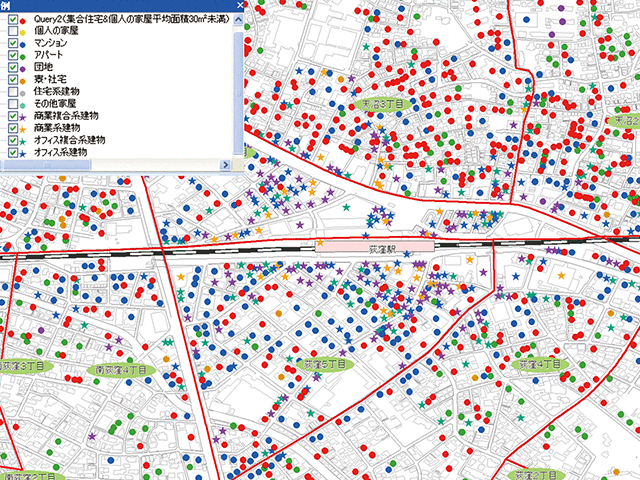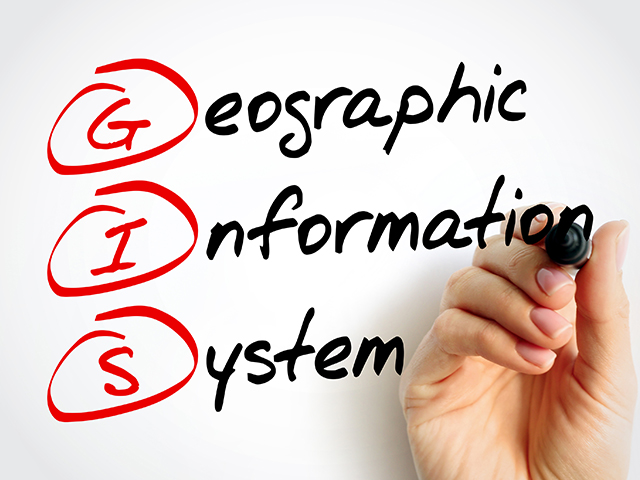Project PLATEAU(プラトー)とは、国土交通省が主導する日本全国の都市の3Dモデル化プロジェクトであり、より高度な都市計画立案や都市活動のシミュレーションなどを行っています。
3Dモデルを使うことにより、スマートシティをはじめとした、都市計画のDX(デジタル・トランスフォーメーション)を進めることが可能です。
本記事ではProject PLATEAUの概要とデータや特徴、活用例を解説します。
スマートシティについては下記リンクをご覧ください。
Project PLATEAUとは
Project PLATEAUとは2020年12月に発足した国土交通省のプロジェクトです。都市空間そのものを3Dで再現する3D都市モデルの整備・活用を進めることで、まちづくりのDX(デジタル・トランスフォーメーション)を進めます。それによって都市計画の高度化や都市活動のより精細なシミュレーションに役立つことや、多様な生き方や暮らし方を支えるサステナブルで人間中心のまちづくりの実現などを目的としています。
Project PLATEAUは単なる3Dの座標データではなく、GISの概念も含んだプロジェクトです。また大きな特徴が、日本各地の3D都市モデルデータをオープンデータとして誰でも使えるようにし、標準化されたフォーマットで記述していることです。これによって開発ナレッジ共有や、データ間の連携促進が図られます。結果として広く利用でき、データ民間市場のサービスや制作物の質向上に役立てることが可能となります。
具体的には、都市の建物や街路の3次元形状をCGモデルで再現し、それに名称や用途・建設年都市などの活動情報を付与した地理空間データです。モデルデータに建築物の用途や建築年が付与できるため、建築物の詳細情報にすぐアクセスでき、ほかのデータやソフトウェアとの連携が円滑に行えます。
Project PLATEAUのデータは、当初全国56都市の都市空間を3Dモデル化して再現していましたが、 2027年度までに約500都市に拡大、将来的に全国整備を目指しています。その後も整備範囲の拡大を進めていきます。災害対策や人流のシミュレーションなどさまざまな分野における課題解決に活かすことが可能です。これを活用することによって、各自治体や企業の担当者はより詳細かつ具体的なリスク解析や商圏分析が実現します。
Project PLATEAUでできることとは
Project PLATEAUで表示される建物の3Dデータには、建物の材質や築年数、高さなどの各種情報が含まれています。都市全域を3Dマップで表示できるため、交通ルートやドローンルートの検証にも役立てられます。
Project PLATEAUでできることは、具体的には以下のとおりです。
建築物の材質や築年数の情報がわかる
3D都市モデルには都市計画基礎調査で収集された建築物の用途や建築年といった属性情報が付与されており、建築物ごとの材質や築年数の情報が記述されています。
この性質を生かすことで、例えば、コンクリートの材質を使用した建物で電波が減衰する度合いや、窓ガラスでどれだけの太陽光が反射するか、といったプログラムを書いてシミュレーションすることが可能です。
属性情報を基に建物を色分けして表示できる
Project PLATEAUのデータに保存されている建築物は、属性情報をベース値とすることで、建物ごとに色分けして表示できます。例えば、あらかじめ設定した高さや用途・建築構造などの値以上の建物だけを黄色で表示し、その値以下の建物は青色で表示するといったことが可能です。
建物単位で浸水リスクのランクを表示することもできるため、あらかじめ津波の高さを設定し、その高さの津波によって浸水する建物だけを色付けして表示することもできます。建物単位で災害リスクを判断できるため、これを活用した防災用のシステム開発にも使用できます。
土地ごとの分析やシミュレーションができる
Project PLATEAUのデータでは、都市全域を対象として土地ごとの分析やシミュレーションも可能であり、スマートシティ化を進める際のセンサーの配置位置検討や都市全体の防犯・防災などに生かすことができます。
地域全体に存在するIoTセンサーの情報を収集し、地域に不審者がいないかを監視して警備員を配置することにも活用することが可能です。
交通状況やドローンルートの実験・検証ができる
Project PLATEAUのデータを活用することで、交通ルートや都市圏内でドローンを飛ばす際の最適なルートを実験・検証することができます。
例えば、トラックやトレーラーなどの大型車両を走らせた際に発生する騒音の影響範囲や、車両が橋にぶつからないか、道路を曲がることができるかといったことを事前にデータ上で実験・検証できます。通常の交通量と大規模施設工事における工事車両の交通量を合わせて分析することで、最適な量の工事車両を最適な時期に移動させることも可能です。
Project PLATEAUのデータの活用例
Project PLATEAUのデータの活用例について解説します。
都市計画の立案
都市全域を対象として分析が可能なため、地域全体を見据えた都市計画の立案が可能です。一部では屋根や壁などの情報も付与されるなど、再現度が高いので、より詳細な計画立案につながります。計画可視化によって、速やかな情報共有や合意形成も期待されます。都市計画にかかる時間そのものも短縮化できるでしょう。
都市活動のシミュレーション
先に挙げたように、交通状況やドローンの最適ルートなどのシミュレーションが可能です。実際の都市活動において「大型の建造物が立つので、日照状況の変化を知りたい/空気の流れがどう変わるか知りたい」など、さまざまな要求に応えることができるのです。交通量や人流をシミュレートすることで、住みやすさや快適さの実現に寄与します。
防災や防犯の対策
Project PLATEAUのデータでは、先に挙げたように津波による浸水でどれだけの被害が出るのか、どの建築物にどれだけの浸水リスクがあるのかなどを可視化し、リスク分析ができます。また、防犯カメラやセンサーを死角や犯罪発生率の高い場所に設置することで、効率的な防犯活動にも役立てることが可能です。
なお、Project PLATEAUが公開している3D都市モデルでは、従来の地理空間情報との重ね合わせもできます。そのため、オープンデータであるProject PLATEAUと民間データを掛け合わせて、土地開発や設計に活用することも可能です。
Project PLATEAUとゼンリン3D地図データの違いとは
弊社が提供する「ゼンリン3D地図データ」は、Project PLATEAUと似た特徴を持っています。ここでは両者の違いについて解説していきます。
建物データの再現レベル
どちらも、建物の高さまで再現します。建物データの高さのレベルにおける再現度合いでは、航空測定等によるProject PLATEAUデータのほうがよりリアルなモデルかもしれません。ただし、Project PLATEAUと比較して「ゼンリン3D地図データ」は、日本全国の建物を細かく再現しているという違いがあります。なお、両者とも建物と高さに加え、「屋根形状」も再現していますが、日本全国を網羅しているわけではありません。
提供範囲や更新頻度の違い
Project PLATEAUの提供データに含まれる範囲は全国57都市であり、更新期間は都市計画整備に依拠していくようです。それに対し、「ゼンリン3D地図データ」は全国のデータを提供しており、更新頻度も年1回と高頻度です。道路表現も形状とテクスチャを再現しています。
また、用途によって以下の3種類のデータが選べます。
⮚3D都市モデルデータ
提供範囲は特別区・政令指定都市含む21都市(中心部分)。建物形状や道路の路面ペイント、高架等の立体表現等を再現
⮚広域3次元モデルデータ
提供範囲は全国の都市。広域の3Dモデルデータを提供。建物の形状と階数情報を基に全国をモデル化した3D地図データとして再現
⮚DXFデータ
提供範囲は全国の都市。2Dと3Dでの表示が可能。建物形状が表現されており、3Dは高さも表現
Project PLATEAUとゼンリン3D地図データを使い分けることでより詳細な分析・活用ができる
Project PLATEAUで提供されるデータは高精度の3D都市モデルを含めており、建築物情報をひと目で閲覧でき、防犯・防災や交通・人流のシミュレーションなど、さまざまな事柄に使うことができます。
建物データはProject PLATEAU、道路データはゼンリン3D地図データといったように、お互いの特徴によって使い分けることで、より高品質な地図データを作成できます。
また、ゼンリン3D地図データは、弊社が保有する属性情報が入った「建物ポイントデータ」を紐づけることで、BIMでの活用や災害シミュレーション、メタバースなどさまざまな用途で活用することもできます。データ活用の利便性向上を目指したい方は、ぜひご検討にしてください。